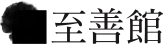地域医療の再生を目指し、医師として、経営者として、自らの使命を問い直す
今野 健一郎さん(Class of 2025|株式会社Carus Holdings 創業医師)
– ご自身について、簡単に紹介いただけますか?
出身は宮城県で、父は建築士、母は看護師という家庭で育ちました。10代の頃は、ピアニストか、あるいは文学や社会学の研究者になることを夢見ていました。
結局、音楽の才能には限界を感じ、母の従事していた医療分野に進むことを決め、大学は医学部を選択しました。大学卒業後は沖縄や東京の病院で8年間、臨床医として目の前の患者さんのために全力を尽くす日々を送りました。しかし、もともと音楽や文学など一人で何かと向き合うことが好きな性格もあり、大きな組織の一員として働くよりも、小さくてもいいから自分の城を築きたい、という思いに至って、35歳だった2018年に、栃木県にある3代に渡っておよそ半世紀続いたクリニックを事業承継する形で、開業医としてのキャリアをスタートさせました。
当初は、医師としての残りの人生、一つの場所で地域に根差した町医者として過ごせれば、と考えていました。しかし、いざ地域医療に身を置いてみると、地方の医療従事者の平均年齢がとても高い、という現実に直面しました。所属していた地区の医師会の平均年齢がおよそ70歳だったりと、地域の医療インフラが想像以上に高年齢化、身もふたもない言い方をすれば、疲弊していました。全国的に見ると、診療所の9割、病院の7割以上に後継者がいないという現実もありました。
このままでは、地域の医療システムが崩壊してしまう、という危機感が、私を一人の医師から「経営者」へと意識を転換させるきっかけになりました。2020年に医療法人を設立し、後継者のいないクリニックの事業承継と再生の事業を本格的に進め始めました。
– なぜ、数あるMBAの中から至善館を選んだのですか?
事業を展開する中で、新たな壁にぶつかりました。それは、組織をどう成長させていけば良いのか、という経営者としての課題でした。自分が診療行為をするのではなく、法人代表者として、スタッフに士気高く気持ちよく動いてもらうためには、自分がリーダーとして、個人事業主から成長・脱皮する必要がありました。経営のスキルを上げつつ、自分の器を広げて、地域医療の再生という大きな社会課題と対峙するための強い組織を作る必要がありました。
他校の単科生になって特定分野の勉強したりもしましたが、従来のMBAが教えるようなフレームワークやスキル教育だけでは、複雑に絡み合う医療現場の課題は解決できないし、自分の経営者としてのあり方を見つめ直すには、物足りないと感じていました。
その点、至善館は、経営学とリベラルアーツが深く融合した、他に類を見ないカリキュラムだと思いました。至善館は、経済合理性を追い求めた米国型のMBAを超えたリーダーシップ教育を提供しようとしていて、ここでなら自分が求めている経営者としての成長が期待できると思いました。個人的には、人文系のファカルティ陣が非常に豪華だったのも魅力でした。
– 実際に学んでみて、至善館の魅力をどう表現しますか?
至善館での2年間は、まさに期待以上のものでした。至善館の授業では、私たちに知識を教えるのではなく、常に「あなたは、どうするのか?」「あなたの持論は何か?」と、一人ひとりの当事者意識を鋭く問い続けます。
臨床の現場で診断や治療方針について「正解探し」の癖が染み付いていた私にとって、この「正解のない問い」に向き合い続けることは、苦しくも、非常に刺激的な経験でした。自分の意見を述べると、教員やクラスメートから「本当にそうか?」「別の見方はないか?」と、あらゆる角度から揺さぶりがかかります。自分の思考の偏りや、いかに自分が狭い世界で生きてきたかを痛感させられる毎日でした。
しかし、そのプロセスを通じて、多様な価値観を受け入れ、複雑な状況の中から自分なりの「軸」を見出し、意思決定していく力が、確実に養われていったと感じます。これは、教科書を読んでいるだけでは決して得られない、至善館ならではのライブな学びでした。
また、2年間を通じて、リーダーに必要な「人としてのあり方」や「誠実さ」「一貫性」「高潔さ」について深く考え続けることができました。医師になると、若くして周りからは「先生」と呼ばれるようになり、人間的な成長がなくともクリニックの院長や社長として立場が上がるだけで、知らず知らずのうちに傲慢になっていた自分に気づきました。至善館で学ぶことでその姿勢を見つめ直し、まだ自分には成長の余地があることを実感できました。
– 卒業後、仕事やキャリアにどのような変化がありましたか?
至善館での2年間は、F1のレースで言うと、「ピットイン」のようなものだったと、今振り返って感じています。日々の診療や経営という、休む間もなく走り続けなければならない「日常生活」「日々の仕事」というサーキットから一時的に離れ、自分自身と組織を冷静に見つめ直す貴重な時間でした。オペレーションに追われる日常では、つい「How(どうやるか)」ばかりに目が行きがちです。しかし、至善館では「Why(なぜやるのか)」「What(何をやるべきか)」という、より根源的な問いと向き合います。それも、多様な環境に身を置くクラスメイトと一緒に未来について考え、議論し、新しい視点を得る、というプロセスは、思考を定期的に「メンテナンス」するような感じでした。ピットインで、頭を整理し、日常に戻る、ということを繰り返す中で、至善館で学んだ抽象的なことと、日常で起こる具象を結びつけながら仕事ができました。
その中で、トップダウンで組織を引っ張るだけがリーダーシップではないこと、多様なメンバーの力を引き出し、自律的な組織を創ることの重要性も学びました。卒業に向けた個人プロジェクト*では、素晴らしい指導役の先生とチームメンバーに恵まれ、自社の事業課題と社会課題を結びつけ、具体的なアクションプランに落とし込むことで、学びを実践へと繋げる経験も積むことができました。
– 至善館に応募しようとしている将来の仲間へメッセージをお願いします。
医療・介護の現場では、物価や人件費の高騰、診療報酬制度の遅れ、外来患者の減少など、これまでの常識が通用しない大きな転換期を迎えています。かつては「真面目に診療すればよい」時代でしたが、今はそれだけでは医療機関を持続的に運営することが難しくなっています。
これからの医療には、経営感覚を持ち、社会全体を見渡しながら「未来の医療・介護のあり方」を構想できる人材が必要だと思います。医療の現場を理解しながら、MBA的なマネジメント知識と全人格な素質を備えた人が増えることで、地域社会はより健全に発展していくと信じています。
至善館で学ぶことは、単なる経営知識の習得にとどまりません。人としてのあり方や哲学を磨き、医療という専門領域を超えて社会を変える力を育む場だと思います。これからの時代を担う医療・介護従事者の方々にこそ、ぜひ至善館で学んでほしいと思います。
今年、卒業生や在校生に加えて、至善館の外から医療従事者たちが集う「メディカル・インパクト・ナイト」**という公開イベントを立ち上げました。これは、至善館で得た学びを、医療界に広げたいという想いから生まれたものです。孤立しがちな医療界のリーダーたちが領域を超えて繋がり、学び合うプラットフォームを創っていきたいと考えていて、今後もシリーズ化して開催を予定しているので、ぜひこちらにも参加して欲しいです。
(2025年10月17日)
*至善館では、修士論文の代わりに、学生一人一人が2年間の学びを統合し、卒業後の展望を「事業構想書」としてまとめます。
**Medical Impact Night
社会が抱える医療課題に直接アプローチし、インパクトを生み出したいと真剣に考える人たちの集い。一般公開イベントとして開催。医療・介護・福祉の分野で新しい挑戦を続ける実践者をお迎えし、参加者の皆さんと共に知見を交わし合うことで、次の一歩を考える時間を提供しています。