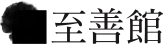2025年11月6日(木)、大学院大学至善館の日本橋キャンパスにて、「第1回Medical Impact Night」が開催されました。本イベントは、至善館のインパクト・エコノミーセンターが主催する「Impact Night」から派生した新企画です。医療、介護、福祉といった領域で社会課題解決に取り組む情熱を持つ人々が集い、未来に向けた対話と交流を深めることを目的としています。
記念すべき第1回のゲストには、鳥取大学医学部地域医療学講座の孫大輔准教授が登壇。モデレーターは、至善館の修了生(2025年卒)であり、株式会社Carus Holdingsの創業者兼代表医師でもある今野健一郎さんが務めました。
卒業生から見た至善館の学びと本イベントへの期待
イベントは、モデレーターである今野さんの挨拶から始まりました。自身も医師として地域医療の再生に取り組む経営者である今野さんは、至善館が単なる経営スキルだけでなく、「我々はどこから来たのか、何者なのか、どこへ行くのか」といった根源的な問いを通じて、全人格的なリーダーシップを育むユニークな経営大学院であることを紹介しました。
その上で、今回のMedical Impact Nightが、専門領域の壁を越えて多様な参加者が集い、新たな視点や繋がりを生み出す場となることへの期待を語りました。
孫大輔氏による講演:アートや対話が拓く、新しい医療のカタチ
続いて、孫大輔氏が登壇し、「社会的処方から文化的処方へ」と題した自身の多彩な活動について語りました。
孫氏は、医療の現場で感じる課題意識から、地域社会に積極的に関わる活動を展開しています
孫氏の主な活動:
- 病院から「まち」へ: カフェで市民と医療者が自由に対話する「みんくるカフェ」や、地域資源を活用して住民の健康増進を目指す「谷根千まちばの健康プロジェクト」などの他、医師や看護師が屋台を引いて街へ出て、コーヒーを振る舞いながら住民とゆるやかな対話の場を創出したり、健康への無関心層とも接点を持つことで、地域のウェルビーイング向上に繋げた様々な事例が紹介されました。
- 映画制作を通じた文化的処方の取り組み: 自ら監督・脚本を手がけ、在宅での看取りをテーマにした映画「うちげでいきたい」等を制作。この映画の上映会を全国各地で行い、参加者同士が死生観や地域の医療について語り合うワークショップへと繋げている経験を共有いただきました。
- 医療人文学(Health Humanities)の実践: 文学や哲学、アートといった人文学の知見を医療教育や実践に活かす「医療人文学」の取り組みを紹介。答えのない問いを考え続ける力(ネガティブ・ケイパビリティ)を養うことの重要性が強調されました。
孫氏は、病気の方へ薬の処方をはじめとした治療を行うだけでなく、人との繋がりや文化・芸術活動などを通じて人々のウェルビーイングを高めようとする考え方に基づき行動されています。「ゆるいつながり」や「たまり場」といった地域社会のソーシャルキャピタルが人々の心身の健康に与える影響の大きさを指摘し、アートや対話が持つ力を通じて、より人間的な医療のあり方を模索していると語りました。
参加者との対話、そして未来への展望
講演後、参加者はグループに分かれて感想や意見を交換し、活発な議論が交わされました。その後の質疑応答では、「こうした活動をいかにして持続可能なものにしていくか」「AI時代における医療者の役割はどう変わるか」といった鋭い質問が寄せられました。
孫氏は、「活動の持続性には、行政との連携や事業化など様々な形があり、私自身も模索している。しかし、活動を通じて生まれる当事者たちの変容や、地域との相互作用そのものに大きな価値がある」と答えました。
最後に、至善館副学長でありインパクトエコノミーセンター長を務める鵜尾雅隆が総括を行いました。鵜尾は、孫氏の活動を「社会的なR&D(研究開発)」と位置づけ、「既存の枠組みからはみ出し、新しい価値を創造しようとする実践者こそが、未来の社会システムを構想する上で不可欠なロールモデルとなる」と述べました。そして、セクターを越えた協働の中から社会課題解決の新たなソリューションを生み出していくことの重要性を強調し、イベントを締めくくりました。
イベント終了後には懇親会が開かれ、参加者と登壇者が飲み物を片手に和やかに歓談し、交流を深めました。
「Medical Impact Night」は今後も定期的に開催予定です。次回は2026年1月23日に、感染症対策や地域医療の専門家である高山義浩氏をゲストに迎える予定です。